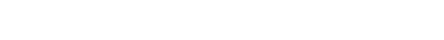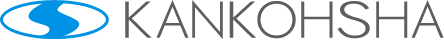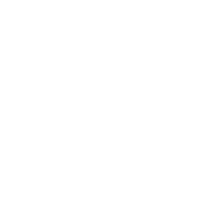Corporate Message
美しさを追求し あなたの一歩を支える
私たちは、人々の生活に「美と健康」をもたらす素材を追求し、
お客様から安心と信頼を得られる確実な商品を提供し、社会に貢献します。
Scroll
ABOUT
感光社とは?
美しく活きるヒトを支える・・・これは感光社創業からの変わらない思いです。そして、これからも美しく活きるヒトを支えるために、感光社は変わり続けます。
-

化粧品の原料販売(感光素・糖製品・その他天然原料等)
(感光素・糖製品・その他天然原料等)
地球環境を守りながら、美を追求するための天然 及び 植物由来を主とするサステナブル(持続可能)な化粧品原料を販売を行っております。
地球環境を守りながら、美を追求するための天然 及び 植物由来を主とするサステナブル(持続可能)な化粧品原料を販売を行っております。
-

健康食品の原料販売
原料の素材、栄養、めぐみを大切にしたい、安心・安全なオーガニック・無添加にこだわった商品、私たち自身が「食べたい」と思うものを販売しております。
原料の素材、栄養、めぐみを大切にしたい、安心・安全なオーガニック・無添加にこだわった商品、私たち自身が「食べたい」と思うものを販売しております。
ACHIEVEMENT
取引先企業
- 味の素ヘルシーサプライ 株式会社
- 大塚製薬 株式会社
- 香椎化学工業 株式会社
- 株式会社 アリエ
- 株式会社アルビオン
- 株式会社 アンズコーボレーション
- 株式会社 カナエテクノス
- 株式会社 加美乃素本舗
- 株式会社 クラブコスメチックス
- 株式会社 コーセー
- 株式会社 コスモビューティー
- 株式会社 サティス製薬
- 株式会社 資生堂
- 株式会社 シャンソン化粧品
- 株式会社 スタイリングライフホールディングスBCLカンパニー
- 株式会社セレス
- 株式会社 ちふれ化粧品
- 株式会社 ディーエイチシー
- 株式会社 日本色材工業研究所
- 株式会社 ノエビア
- 株式会社 ハーバー研究所
- 株式会社 ピカソ美化学研究所
- 株式会社 ピクシー中央研究所
- 株式会社 ファンケル美健
- 株式会社 マーナーコスメチックス
- 株式会社 マンダム
- 株式会社 ミルボン
- 株式会社 ヤクルト本社
- 銀座ステファニー化粧品 株式会社
- 小林製薬 株式会社
- ジェイオーコスメティックス 株式会社
- 資生堂ホネケーキ工業 株式会社
- シミックCMO 株式会社
- タカラベルモント 株式会社
- 東色ピグメント 株式会社
- 東洋ビユーティ 株式会社
- 中野製薬製造 株式会社
- 日油 株式会社
- 日華化学 株式会社
- 日本コルマー 株式会社
- 日本ゼトック 株式会社
- 日本メナード化粧品株式会社
- ハリウッド 株式会社
- ピアス 株式会社
- ポーラ化成工業 株式会社
- 御木本製薬 株式会社
- 持田製薬 株式会社